母子家庭で生活をしている世帯にとって、母親が病気で働けないといった状態は大きな問題になります。と言うのは、母子家庭世帯のほとんどは母親が働き、収入を得ていることによって生活しているからです。
怪我や病気で働けないということになった時、真っ先に困るのは生活費をどうするか、でしょう。養育費をもらっていても、それだけで生活していけるケースはほとんどなく、何らかの収入が必要です。
そんな生活に直結するような問題において、母子家庭を援助するような様々な手当が存在することをご存知でしょうか。
どんな手当があるか知っていて、すでに支給を受けている方も多いと思いますが、それでも「これは知らなかった」という支援制度もあるかもしれません。もしまだ支援を受けていないのであれば、すぐに申請したいですよね。
そこでここでは、母子家庭が利用可能な手当てと支援制度についてご紹介します。
児童手当
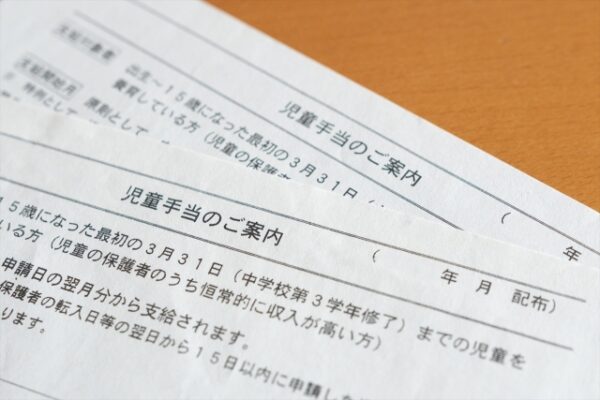
児童手当は、母子家庭だけでなくすべての世帯に支給される手当金です。中学校までの児童を養育している方が対象です。
支援時期は年間3回行われ、6月と10月、そして2月の3回で、ご自身が指定した銀行口座に振り込まれます。
ただし、子供の人数や所得制限によって支給される金額が変わりますのでご注意ください。
支給額
| 子供の年齢 | 支給額 |
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 |
所得制限額
所得制限については複雑なため、内閣府のホームページを参照下さい。
児童育成手当

児童育成手当とは18歳までの児童を扶養している母子家庭が対象です。一人当たり13,500円が支給されます。
こちらも所得制限があり、扶養する子供の人数によってその上限が定められています。
| 子供の数 | 所得制限額 |
| 一人 | 3,984,000円未満 |
| 二人 | 4,364,000円未満 |
| 三人以降 | 4,364,000円に一人当たり380,000円を加算した額未満 |
児童扶養手当
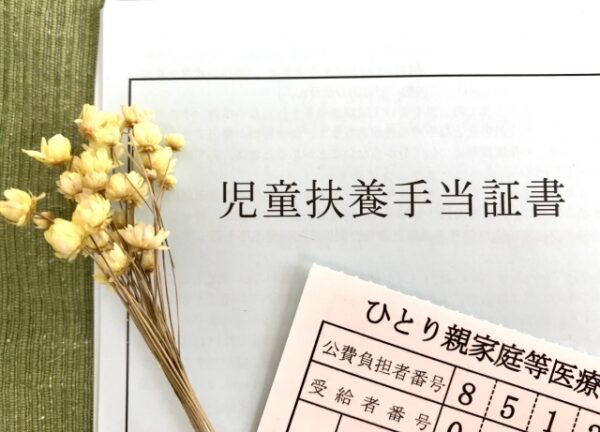
児童扶養手当は、母子家庭や父子家庭の児童扶養している家庭が対象です。
児童育成手当と似ていますが、所得制限の対象が異なり、児童育成手当は受給者のみで児童扶養手当の場合は、受給者のほかに扶養義務者の所得も対象になってきます。
支給金額は、扶養人数や所得によって異なります。
| 子供の数 | 全額支給 | 一部支給 |
| 一人 | 43,070円 | 10,160円~43,060円 |
| 二人 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
| 三人 | 6,100円 | 6,090円~3,050円 |
病気で働けないなどの事情があり、所得が下がれば、それだけ支給額が上がる仕組みです。
また所得制限は二人世帯の場合、全部支給になるのは収入160万円、一部支給うになるのは年収365万円です。詳しくは厚生労働省のホームページを参照下さい。
病気で働けない母子家庭への住宅支援

病気で働けない母子家庭にとって、安全で安定した住まいは生活の基盤となります。住宅支援制度を利用することで、住宅費の負担を軽減することが可能です。
ただしこれは市区町村独自の制度のため、実施してない市区町村もありますので、ご自分の地域が適応しているか調べてみる必要があります。金額も市区町村によって変わってきます。
住宅支援を受けるための条件
支給条件は、市区町村によって異なってきますが、代表的なものとして以下が挙げられます。
- 母子家庭で20歳未満の子供を扶養している。
- 民家アパートに住んでいて申請している住所地に住民票があること。
- 申請していたアパートの住所地に6ヶ月以上住んでいる事
- 生活保護を受けていないこと
支給される金額
支給される金額については、平均で月額5000円から10,000円ほどです。それほど大きな金額ではないかもしれませんが、それでも生活費の足しになり、助かりますよね。
住宅支援の申請方法とその手続き
住宅支援の申請は、住んでいる市町村の福祉課や住宅課で行います。申請に必要な書類は、住宅契約書や収入証明書などです。これらの書類を揃えて申請を行い、市町村からの審査を受けます。
審査結果に基づいて住宅支援の支給が決定され、支給が開始されます。申請から支給開始までの期間は、状況によりますが、約1ヶ月程度と考えて良いでしょう。
母子家庭の子供の医療費助成制度

子供の医療費の自己負担額の一部を市区町村が負担してくれます。対象になるのは、18歳に到達して最初の3月31日までの年齢の子どもがいるひとり親世帯です。
しかし、所得制限があり、一定の所得を超えていると、この制度を利用することができません。
| 子供の数 | 所得制限額 |
| 一人 | 230万円 |
| 二人 | 268万円 |
| 三人 | 306万円 |
| 子供四人以上 | 一人当たり38万円加算 |
母子家庭の遺族年金

不幸にも配偶者が死亡して母子家庭となってしまった場合、ご本人が受け取る予定だった厚生年金の4分の3の金額が支給されます。配偶者が亡くなるなどな精神的なショックを受け、うつ病などの病気で働けないといった状況でも、一定の収入を得られる制度になっています。
ただし、支給される金額は、死亡した親権者が加入していた年金や、子供の有無などによって変わってきます。遺族基礎年金は780,900円で、子供が1人から2人の場合、1人あたり224,700円を加算します。
受け取ることができる期間は、子供が18歳になるまでです。
遺族厚生年金は、子供のいない妻などが対象になります。受け取れる期間は、妻が死亡するまでです。
ところが例外的に早くして配偶者をなくした場合、30歳未満であったケースなどでは、子供が18歳に達するなど、基礎年金の資格を失効してから5年間で停止されます。
生活保護

生活保護は、国が必要最低限の生活を保障しながら、本人が自立することを目的に作られた制度です。
母子家庭の母親が病気で働けないといった状況が続き、生活が困窮してしまった場合、最後の手段として考える支援です。支援対象になるのか確認をお勧めします。
生活保護を受けるための条件
生活保護を受けるには、3つの条件があります。
- 援助してくれる身内や親戚がいないこと。
- 資産を持っていないこと(貯金や持ち家、車を持っている場合は、資産を売却し無ければ、生活保護を受けることができません)
- 病気で働けないなどのやむを得ない事情で働けない場合
月収が最低生活費を下回っており、かつ上記3つの条件を満たしている場合は、生活保護を受けることができます。
生活保護の申請方法とその手続き
生活保護の申請は、住んでいる市町村の社会福祉課や生活保護課にて行います。まず、相談窓口で生活状況や収入、財産などを説明し、申請の適用可能性を確認します。その後、必要書類を揃えて正式な申請を行い、市町村からの調査を受けます。
調査結果に基づいて生活保護の支給が決定され、支給が開始されます。申請から支給開始までの期間は、状況によりますが、約1ヶ月程度と考えて良いでしょう。
生活保護は恥ずかしいと思うような方もおられるでしょう。しかし、最低限の生活を保障するしっかりとした制度なので、大切な子供のためにもちゃんと申請をして利用するようにしましょう。
病気で働けない母子家庭の子どもの教育支援

病気で働けない母子家庭にとって、子どもの教育は大切な課題です。教育支援制度を利用することで、教育費の負担を軽減することが可能です。
子どもの教育支援の申請方法とその手続き
子どもの教育支援の申請は、住んでいる市町村の教育委員会や子ども家庭支援課で行います。申請に必要な書類は、学校の在籍証明書や収入証明書などです。これらの書類を揃えて申請を行い、市町村からの審査を受けます。
審査結果に基づいて教育支援の支給が決定され、支給が開始されます。申請から支給開始までの期間は、状況によりますが、約1ヶ月程度と考えて良いでしょう。
子どもの教育支援を受けるための条件とは
子どもの教育支援を受けるためには、収入が一定の基準以下であること、子どもが学校に在籍していることなどが条件となります。また、病気で働けない母子家庭の場合、母親の健康状態や子どもの年齢などにより、教育支援の申請が認められる可能性があります。
病気で働けない母子家庭の現実

「母子家庭 病気で働けない」という言葉だけで、多くの困難を抱える家庭の現状が伝わってきます。病気になることは誰にでも起こり得ること。しかし、母子家庭でその状況に直面した場合、その影響は計り知れません。
母子家庭で病気になったときの生活の変化
母子家庭で病気になると、日常生活は一変します。健康な時は気にせずにできた家事や子育てが一苦労となり、日常の小さなことが大きな壁となることもあります。外での仕事を持っていた場合、休職や退職を余儀なくされることも考えられます。また、病気の治療や通院に伴う経済的な負担も増えるため、生活の質が低下することも少なくありません。
家事に関して言えば、病気の状態によっては料理や掃除、洗濯などの基本的な家事が困難になります。特に、体力を必要とする家事や、立ち仕事が多い家事は疲れやすくなります。これにより、外食やデリバリーを利用することが増え、食費が増加する可能性があります。
子育ての側面では、子供の送り迎えや学校行事への参加が難しくなることが予想されます。また、子供との遊びや散歩などのアクティビティも制限されることが多く、子供とのコミュニケーションの機会が減少する恐れがあります。
外での仕事を持っていた場合、休職や退職を考慮することも出てきます。特に、体力を必要とする仕事や、長時間の立ち仕事は継続が難しくなります。これにより、収入が減少し、経済的な困難が生じる可能性が高まります。
病気の治療や通院に伴う経済的な負担も増えるため、生活の質が低下する恐れがあります。治療費や薬代、通院のための交通費など、病気になることで発生する出費は少なくありません。これにより、節約や生活の見直しを考える必要が出てきます。
病気で働けない時の日常の過ごし方
病気で働けなくなった母子家庭の日常は、健康時とは大きく異なります。多くの時間を家で過ごすことになるため、家の中でできる趣味や子供との過ごし方を見つけることが大切です。また、外出が難しい場合でも、窓からの景色や音楽を楽しむなど、小さな幸せを見つけることが心の支えとなります。
例えば、読書や手芸、絵を描くなどの静かな趣味は、体力をあまり使わずに家の中で楽しむことができます。また、子供と一緒に絵本を読んだり、手作りのおもちゃで遊ぶなど、子供との時間を大切にする方法もあります。
外出が難しい場合、家の中からでも楽しめることを見つけることが重要です。窓からの景色を楽しむ、音楽を聴く、映画やドラマを見るなど、日常の中で小さな楽しみを見つけることで、心のリフレッシュや気分転換ができます。
また、病気の状態に応じて、短時間の散歩や庭でのガーデニングなど、外の空気を感じる活動も取り入れると良いでしょう。これにより、気分がリフレッシュされ、日常生活に活力が戻ります。
病気で働けない母子家庭の就労支援

病気で働けない母子家庭にとって、将来的に働けるようになるための支援は重要です。就労支援制度を利用することで、就労に向けた準備やスキルアップを進めることが可能です。
就労支援の申請方法とその手続き
就労支援の申請は、住んでいる市町村の福祉課やハローワークで行います。申請に必要な書類は、健康状態の証明書や収入証明書などです。これらの書類を揃えて申請を行い、市町村からの審査を受けます。
審査結果に基づいて就労支援の支給が決定され、支給が開始されます。申請から支給開始までの期間は、状況によりますが、約1ヶ月程度と考えて良いでしょう。
就労支援を受けるための条件とは
就労支援を受けるためには、就労を希望していること、一定の健康状態であることなどが条件となります。また、病気で働けない母子家庭の場合、母親の健康状態や子どもの年齢などにより、就労支援の申請が認められる可能性があります。
病気で働けない母子家庭が直面する問題

病気で働けなくなった母子家庭が直面する問題は多岐にわたります。経済的な困難はもちろん、心理的なストレスや孤立感も大きな問題となります。
生活費の確保の難しさ
病気で働けなくなると、収入が大幅に減少します。その結果、家賃や光熱費、食費などの基本的な生活費の確保が難しくなります。特に、病気の治療費や薬代などの医療費が増える中で、生活費をどうやって捻出するかは大きな悩みとなります。
母子家庭の場合、収入源が一つしかないことが多いため、その収入が途絶えると、生活の維持が非常に困難になります。家賃の支払いが滞ると、住む場所を失うリスクも考えられます。また、食費を削ることで、栄養バランスの取れない食事を取ることが増え、健康を害する可能性も高まります。
さらに、病気の治療費や薬代などの医療費が増える中で、生活費をどうやって捻出するかは大きな悩みとなります。公的な支援を受けるための手続きや、地域の支援団体への相談など、さまざまな方法を探る必要があります。
支援制度の利用
公的な支援としては、医療費の一部を補助する制度や、低所得者向けの生活保護などが考えられます。しかし、これらの制度を利用するためには、所得や家族構成、病状などの条件を満たす必要があり、手続きも複雑です。
地域の支援団体では、病気の人やその家族をサポートするための情報提供や相談窓口を設けていることが多いです。また、病気や障害を持つ人のための就労支援や、子供の教育に関する助成金の情報なども提供されています。
病気になった際の経済的な不安を軽減するためには、早めの情報収集と、適切な制度や支援を利用することが重要です。また、近隣の住民や友人、親戚からのサポートも大きな助けとなることが期待されます。
節約の工夫
このような状況下で、日々の生活を乗り越えるための工夫や節約術を学ぶことも重要です。例えば、食材のまとめ買いや、安価なレシピの活用など、少しの工夫で生活費を節約する方法も存在します。
食材のまとめ買いは、大量購入の際の割引やセールを利用することで、1品あたりのコストを下げることができます。特に、日持ちする食材や冷凍できるものは、ストックしておくことで無駄な出費を減らすことができます。
また、安価なレシピの活用により、高価な食材を使わずに美味しい料理を作ることが可能です。インターネットや料理本で、予算に合わせたレシピを探すことで、家計を助けるとともに、家族の健康を維持することができます。
その他にも、電気やガスの使用量を見直すことで、光熱費の節約が期待できます。例えば、電気の使用時間を短縮したり、冷暖房の設定温度を適切にすることで、少しの節約が積み重なり、大きな節約となります。
子供の教育や将来への不安
病気で働けない母子家庭では、子供の教育費や将来への不安が増します。学校の教材費や習い事の費用、進学に必要な費用など、子供の成長とともに増える出費に頭を悩ませることが多くなります。
小学校や中学校の段階でも、遠足や修学旅行、クラブ活動などで必要となる費用は少なくありません。高校や大学に進学する場合、入学金や授業料、教材費などの大きな出費が必要となり、これをどのように捻出するかが課題となります。
また、子供が大学や専門学校に進学する場合、住居や生活費も考慮しなければなりません。特に、遠方の学校を選んだ場合、一人暮らしの費用や交通費が増加し、経済的な負担が大きくなります。
このような状況下で、奨学金や公的な支援を利用することを検討する家庭も多いです。しかし、奨学金は返済が必要な場合が多く、将来的な負担となる可能性も考慮する必要があります。
在宅でできる仕事

母子家庭で母親が病気で働けないという状況は、非常に厳しいものです。しかし、現代社会では、自宅で働くことが可能な仕事や、自分のスキルを磨く方法がたくさんあります。
そこで次に、「在宅でできる仕事」と「スキルアップと資格取得」について、解説していきます。いずれも、母子家庭で母親が病気で働けない人に対する心強い支援になるでしょう。
まず自宅で働くことが可能な仕事の一部を紹介します。これにより、体調を考慮しながらでも働く可能性が広がります。またリモートワークが普及して自宅で働くことが一般的になりつつあります。これにより、母親が病気であっても、自宅で働くことが可能になります。
データ入力やライティングの仕事
母子家庭で母親が病気で働けないという状況でも、自宅でできる仕事があります。それがデータ入力やライティングの仕事です。
データ入力
データ入力というのは、企業が提供するデータをシステムに入力する作業で、パソコンとインターネット環境があれば自宅からでも可能な仕事です。
データ入力の仕事の特徴は、働く時間を自由に決められるので体調を考慮しながら働くことができること、特別なスキルや経験は必要なく、基本的なパソコン操作ができれば始められることです。
ライティング
ライティングというのは、記事やブログの作成、ウェブサイトのコンテンツ作成など、文字を使った情報の提供を行う仕事です。この仕事も自宅ででき、働く時間を自由に決められます。
また、特定の分野に詳しい、または学びたいという意欲があれば、その知識を活かしてライティングの仕事をすることが可能です。ライティングのスキルは、継続的に書くことで自然と身につきます。
こういった仕事は、母子家庭で母親が病気で働けないという状況でも自宅で自分のペースで働くことができ、収入も得ることができるので、母親自身の自立の支援にもなっています。
リモートワーク
リモートワークとは、自宅やカフェなど、オフィス以外の場所で働くことを指します。最近では、新型コロナウイルスの影響もあり、多くの企業がリモートワークを導入していますが、母子家庭で母親が病気で働けないという方にとっても、リモートワークは大きな助けになっています。
リモートワークには、様々な職種があります。例えば、カスタマーサポートでは、顧客からの問い合わせに電話やメールで対応します。また、プログラミングでは、ソフトウェアの開発やウェブサイトの作成を行います。さらに、デザインの仕事では、グラフィックデザインやウェブデザインなどを行います。
これらの仕事は、自宅で働くことが可能であり、自分の体調や生活リズムに合わせて働くことができます。これは、母子家庭で母親が病気で働けないという状況でも、自分のペースで働き、収入を得ることができる大きなメリットです。
また、リモートワークは、通勤時間がないため、その時間を自分自身のスキルアップや家庭のために使うことができます。これにより、仕事と家庭生活のバランスを保つことが可能になります。
在宅で学べるオンラインコース
母子家庭で母親が病気で働けないという状況でも、自宅でスキルを磨くことは可能です。その一つの方法が、オンラインコースを利用することです。
オンラインコースは、インターネットを通じて提供される教育プログラムで、自分のペースで学ぶことができます。これは、体調を考慮しながらでも学び続けることができる大きなメリットです。また、多くのオンラインコースは、自宅で学べるだけでなく、スマートフォンやタブレットからでもアクセスできるため、場所を選ばずに学ぶことができます。
オンラインコースは、様々な分野で提供されています。例えば、プログラミングのコースでは、初心者から上級者まで、様々なレベルのプログラミングスキルを学ぶことができます。また、デザインのコースでは、グラフィックデザインやウェブデザインなど、デザインの基本から専門的なスキルまで学ぶことができます。さらに、マーケティングのコースでは、デジタルマーケティングやSEOなど、最新のマーケティング戦略を学ぶことができます。
これらのオンラインコースを利用することで、母子家庭で母親が病気で働けないという状況でも、自宅で新たなスキルを磨き、自分の市場価値を高めることができます。
取得できる資格とそのメリット
母子家庭で母親が病気で働けないという状況でも、自宅で資格を取得することは可能です。資格を取得することは、自分のスキルを証明し、より多くの仕事の機会を得るための有効な手段です。
例えば、英語教育の資格は、英語を教えるためのスキルを証明します。TOEICやTOEFLなどの英語資格は、英語を使った仕事の機会を広げるだけでなく、英語教育の仕事にもつながります。これらの資格は、オンラインで学習し、試験を受けることができます。
また、IT分野の資格は、ITスキルを証明します。プログラミングやウェブデザイン、データ分析など、IT分野の資格は多岐にわたります。これらの資格は、IT分野での仕事の機会を広げるだけでなく、リモートワークの機会も増やします。
資格取得のための学習リソースは、オンラインで多数提供されています。これにより、母子家庭で母親が病気で働けないという状況でも、自宅で新たな資格を取得し、自分の市場価値を高めることができます。
病気で働けない母子家庭への応援の声
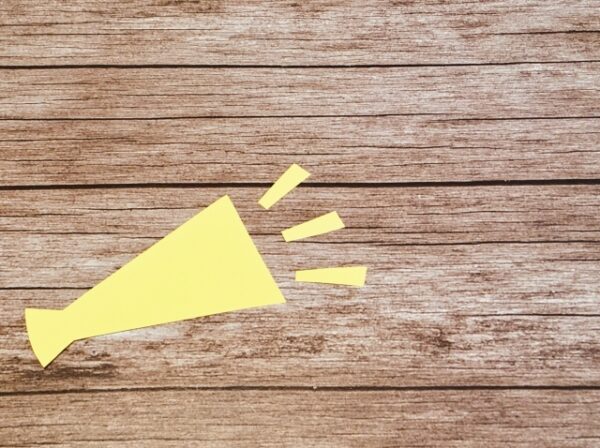
病気で働けない母子家庭には、多くの困難がありますが、同時に多くの人々からの応援の声も寄せられています。
地域や友人からのサポートの大切さ
病気で働けない母子家庭にとって、地域や友人からのサポートは非常に大切です。近所の人や友人からの手続きのアドバイスや、日常生活のサポートなど、小さな助けが大きな力となります。
地域の住民やコミュニティは、病気の母子家庭をサポートするための情報交換の場を提供することが多いです。例えば、子供の送迎や、買い物の代行など、日常生活の中でのサポートを受けることができます。これにより、生活の質を維持することができるだけでなく、孤立感を減少させる効果もあります。
また、友人や知人からは、病気に関する情報や治療法、病院の選び方などのアドバイスを受けることができます。これにより、治療の方向性を見つける手助けとなることが期待できます。
心のサポートも忘れてはなりません。病気の母子家庭は、経済的な問題だけでなく、心の問題も抱えています。友人や地域の住民とのコミュニケーションは、心のケアとしても非常に有効です。
病気を乗り越えるための心の持ち方
病気を乗り越えるためには、前向きな心の持ち方が必要です。病気の状態や治療の進行を受け入れ、自分の体と向き合うこと。そして、家族や友人、地域の人々との絆を大切にし、一緒に乗り越えていくことが大切です。
病気になった際、多くの人は不安や恐れを感じることがあります。しかしその感情に取り込まれることなく、現状を冷静に受け入れることが第一歩となります。病気の受け入れは、治療への取り組みや日常生活の改善に繋がります。
また、自分一人で抱え込むのではなく、家族や友人に感じていることを話すことで、心の負担を軽減することができます。人とのコミュニケーションは、心の安定や回復を助ける要因となります。
病気との向き合い方を見直すことも重要です。病気は一時的なものであり、それを乗り越えるための方法や手段を探求することで、前向きな気持ちを保つことができます。

