母子家庭になるのには様々な理由がありますが、母子家庭になった時、一般的には世帯の収入は減ることになります。
専業主婦であったなら世帯としての収入はなくなり、共働きであったとしても、元夫の収入分が減ります。養育費をもらうことになったとしても、世帯収入は減ることがほとんどでしょう。
実際に、厚生労働省が公表している「全国ひとり親世帯等調査(旧:全国母子世帯等調査)」によれば、母子家庭の世帯収入は、児童のいる世帯全体の平均収入と比べて49.2%に過ぎません。
そのため、普段でも生活費の負担が大きく、子供の教育費などの工面で苦労することは少なくありません。場合によっては貸付金などを利用する必要も出てきます。
そんな時、頼りになるのが自治体が運営する貸付制度です。
自治体が運営する貸付制度で代表的なのは、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度です。母子家庭にとって一番ありがたいのが、利率が低いことでしょう。保証人がいれば、基本的に無利子で借りることができます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、内閣府男女共同参画局が制定し、厚生労働省が運営する貸付金制度で、20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等を対象にしています。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は色々な用途をカバーしており、利用するには制度で決められた条件を満足する必要があります。
ここでは、自治体が行う母子父子寡婦福祉資金貸付金制度で、貸付金を利用する時の条件などについて詳しく解説していきます。
母子父子寡婦福祉資金の貸付金の利用条件とは?

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、貸付対象であれば無条件に借りられるものではありません。審査は厳格に行われます。
審査の対象は貸付金の種類や自治体によって詳細が異なりますが、一般的には以下の3つが利用条件として重視されます。
- 返済能力
- 連帯保証人
- 面接
返済能力
当たり前ではありますが、きちんと返済出来る見込みのある人が対象です。本人の収入と、連帯保証人の返済能力が合わせて考慮されます。
連帯保証人
連帯保証は、借りた人が返済出来ない時、代わりに支払う事を意味します。
「本人から先に取り立てて」と言う事も出来ないため、貸し付ける側としては、連帯保証人さえちゃんとしていれば問題ない、とも言えます。
収入がある現役世代で、貸付金の申込者と生計が別である事が求められます。
全ての種類で連帯保証人が求められる訳ではありませんが、連帯保証人がいた方が金利面で有利になる場合があります。
面接
申込者と連帯保証人の面接も必要となります。名前だけ借りて連帯保証人を立てるような事は出来ません。
次に、具体的な貸付金項目別の条件を見ていきましょう。
母子父子寡婦福祉資金の貸付金項目別の条件とは?
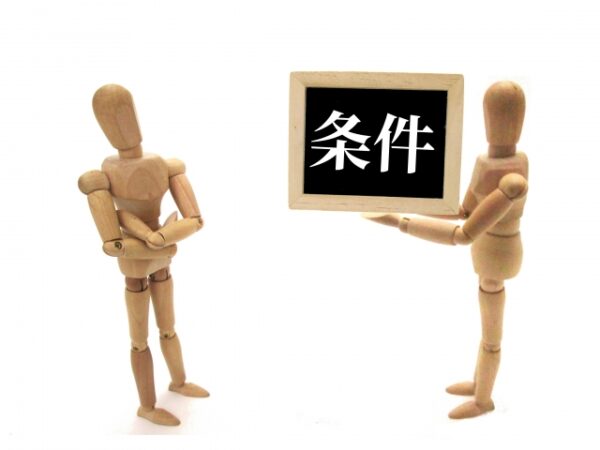
母子父子寡婦福祉資金貸付金の条件について、項目別に見ていきます。
1)転宅資金
母子家庭で、転居が必要になった時の支援を目的とした貸付金です。
支援額は上限260,000円、償還期間は3年以内となっています。
条件として挙げられる対象は、母子家庭の場合「母」となっており、児童が独立する際の転居費用は対象とされません。
利率に関しては、連帯保証人を立てることが出来れば無利子、立てられない場合は1%の利子が必要となります。
2)生活資金
母子家庭の場合、生活安定期間に必要な生活補給資金として貸付を受けられます。
貸付の条件としては、まず、母子家庭になって7年未満である事が挙げられます。
支援額は、母親が生計中心者の場合で月額105,000円、合計252万円となっています。償還期間は、生活安定貸付の場合は8年以内です。
こちらの金利に関しても、連帯保証人を立てる事が出来れば無利子、立てられない場合は年1%の利子となります。
3)修学資金
子供の教育についての資金です。高校~大学院までの授業料や交通費等の資金の貸し付けとなります。
高校から大学院、専修学校など、8種類の学校を対象にし、各学校ごとに支給額が決められています。高校で月額52,500円、短期大学で月額131,000円、大学で月額146,000円、専修学校で月額51,000円となっています。
償還期間は、専修学校の5年以内を除いて20年以内と最も長く、利率は無利子です。
利用する場合の条件として、特に連帯保証人に関する記述があります。
具体的には、貸付金を親と児童のどちらに貸し付けるかによって、条件が異なります。親に貸し付けられた場合は児童を「連帯借受人」とする必要があります。
連帯貸借とは、その貸付金を親子で一緒に借りているという意味です。両者が返済義務を負い、貸した側もどちらに返済を請求しても良いというものです。
児童に貸し付けられた場合、親などが「連帯保証人」となる必要があります。
4)就職支度資金
こちらは、就職するために直接必要な被服(衣類、靴、帽子など)や、通勤用の自動車などを買う為の資金です。
母子家庭の場合支給対象は「母又は児童」となっており、条件の中に母親自身の就職も含まれます。
支援額は通常で100,000円、償還期間は6年以内です。通勤のために自動車を購入する場合は支給額は330,00円となります。
児童への貸付の場合、親が連帯保証人になる必要があります。
親への貸付の場合は、連帯保証人を立てる事が出来れば無利子、立てられない場合は1%の利子が必要です。
5)技能習得資金
就職したり自分で事業を始める際に必要になる知識、技能を習得するために必要になる費用をまかなう資金です。
対象は、母子家庭では「母」になります。
支援額は上限で月額68,000円、償還期間はこちらも20年以内と長く、利率は保証人がいれば無利子、いない場合は年1%です。
6)修業資金
技能習得資金の条件が母子家庭の「母」であったのに対し、母子家庭の「子供」を条件にしているのが修学資金です。
支援額は上限で月額68,000円、償還期間は20年以内、利率は修学資金の場合と同じとなっています。
7)住宅資金
住宅を購入、あるいは建設する、今の住宅を補修する、改築、増築等する際に必要になる費用をまかなう資金です。
支援額は通常の貸付で上限1,500,000円、償還期間は6年以内、利率は保証人がいれば無利子、いない場合は年1%です。
このほかにも、結婚資金、医療介護資金、事業開始資金、事業継続資金があります。
母子父子寡婦福祉資金の貸付金、返済計画も条件になる?

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、民間の金融機関からの借金と比べると、遙かに良い条件で借り入れる事ができます。
保証人がいなくても利率は年1%、保証人がいれば無利子で借りられるので、これ以上の好条件はないと言っていいですよね。
ですが、無利子であっても返済計画はきちんと立てる必要があります。
子供の将来を予想しながら、必要なものを計画的に利用するバランス感覚を持ちながら、賢く制度を利用していきましょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付金のメリットとデメリット

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、多くの母子家庭にとって生活を支える大きな支援になっています。この制度の最大の魅力は、低い利率での借り入れが可能であることですが、メリットだけでなくデメリットもあります。
利率が低いことのメリット
低い利率での借り入れは、返済の負担を大きく軽減することができます。特に生活費や教育費など、日常の出費が重なる中での返済は家計に大きな影響を及ぼすことが考えられます。低い利率での借り入れはそのような家計の負担を和らげ、より安定した生活を築く手助けとなります。また低い利率は、長期間の返済においても、総返済額の増加を抑える効果があります。これにより家計の安定性が高まり、将来的な生活設計もしやすくなります。
低利率の背景
母子父子寡婦福祉資金貸付金の低利率は、国や自治体が家庭の経済的な困難を考慮し、支援の一環として設定しています。この制度は、家庭の経済的安定を目的としているため、市場の一般的な金利よりも低く設定されています。
低利率の長期的な影響
低利率の恩恵は、短期的な返済の軽減だけでなく、長期的な視点でも大きなメリットがあります。具体的には、長期間にわたる返済でも、利息の部分が少なくなるため、元金の返済により多くの資金を充てることができます。これにより、返済期間の短縮や、返済後の生活資金の確保がしやすくなります。
低利率と他の金融商品との比較
一般的な銀行ローンやクレジットカードのキャッシングなど、他の金融商品と比較しても、母子父子寡婦福祉資金貸付金の利率は非常に魅力的です。これにより、同じ借入額であっても、返済総額が大きく異なることが考えられます。この差は、長期間の返済を考えると、数十万円、場合によっては数百万円の差となることもあります。
返済計画の重要性
しっかりした返済計画を立てることは、借り入れを行う際には最も重要です。低い利率であっても、計画的に返済を行わなければ将来的に返済が困難になるリスクがあるからです。返済計画をしっかりと立てることで将来的なリスクを回避し、安心して借り入れを行うことができます。
返済計画の基本的な考え方
返済計画を立てる際の基本は、自身の収入と支出を正確に把握することです。月々の収入と固定費、変動費をリストアップし、余剰金額を確認します。この余剰金額を基に、返済金額を設定することで、無理なく返済を進めることができます。
返済期間の設定
返済期間を設定する際は、自身の生活設計や将来の予定を考慮することが大切です。短期間での返済を希望する場合や、長期間にわたる返済を考えている場合、それぞれで返済計画の内容が異なります。返済期間を適切に設定することで、返済の進め方や返済後の生活設計も明確になります。
緊急時の備え
返済計画を立てる際には、緊急時の備えも考慮することが大切です。急な出費や収入の減少など、予期せぬ事態が発生した場合の対応策を考えておくことで、返済計画の途中でのトラブルを避けることができます。例えば、緊急時の資金を確保するための貯蓄や、返済金額の一部を繰り上げ返済することで、返済の柔軟性を持たせる方法などが考えられます。
他の金融機関との比較
多くの金融機関が様々なローンや貸付を扱っています。母子父子寡婦福祉資金貸付金は、その特性上、他の金融機関とは色々と異なります。例えば、審査基準や利率、返済期間など、多くの面で他の金融機関との違いが見られます。他の金融機関との比較を行うことで、自身の状況に最も合った借り入れ方法を選択することができます。
審査基準の違い
母子父子寡婦福祉資金貸付金の審査基準は、一般的な銀行や消費者金融とは大きく異なります。主に、申請者の生活状況や収入、家族構成などが考慮される点です。これにより、一般的な金融機関では難しいとされるケースでも、母子父子寡婦福祉資金貸付金なら審査を通過する可能性があります。
利率の特徴
他の金融機関と比較して、母子父子寡婦福祉資金貸付金の利率は非常に低く設定されています。この低利率は、国や自治体が家庭の経済的な困難を考慮し、経済的な支援の一環としているためです。このような低利率を活用することで、返済の際の金利負担を大幅に軽減することができます。
返済期間の柔軟性
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、返済期間の柔軟性が高いのも、他の金融機関との違いです。特定の期間内に返済を完了させる必要がないため、借り手の生活状況や収入に応じて返済計画を調整することができます。この柔軟性のおかげで、返済の負担を適切に分散させることができます
母子父子寡婦福祉資金貸付金のQ&A

母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する疑問や不明点の中で、よくある質問とその回答をまとめました。
貸付金の審査基準は?
母子父子寡婦福祉資金貸付金の審査基準は、一般的な銀行ローンや消費者金融とは異なります。主に、申請者の生活状況や収入、家族構成などが対象になります。申請者の信用情報も確認されることがありますが、これは過去の返済履歴や延滞情報を確認するためです。
生活状況の考慮
申請者の生活状況は、審査の際に重要な項目となります。例えば、住居の種類や住環境、家族との同居状況などが詳しく確認されます。これらの情報は、申請者の経済的な安定性や返済能力を判断するための基準として使用されます。
収入と家族構成
申請者の収入や家族構成も審査の重要なポイントです。定期的な収入があるか、その収入の安定性、家族の人数や扶養家族の有無などが確認されます。これらの情報を基に、申請者の返済能力や経済的な負担度を評価します。
信用情報の確認
信用情報機関を通じて、申請者の過去の返済履歴や延滞情報が確認されます。これは、申請者が過去に金融機関との取引で問題を起こしていないか、また現在も適切に返済を行っているかを判断するためのものです。信用情報が良好であれば、審査の際に有利となることが考えられます。
審査に通るためのポイント
審査に通るためのポイントとしては、まず正確な情報提供が挙げられます。虚偽の情報を提供すると、審査に通らないだけでなく、将来的にも信用情報に悪影響を及ぼす可能性があります。また、返済計画をしっかりと立て、その計画に基づいて返済を行う意志があることをアピールすることも重要です。
連帯保証人がいない場合の対応は?
連帯保証人がいない場合でも母子父子寡婦福祉資金貸付金の申請は可能です。ただしその場合、返済能力や生活状況がより詳しく確認されることが考えられます。
連帯保証人不要の申請の特徴
連帯保証人が不要な申請の場合、申請者の返済能力が中心となって審査されます。具体的には、申請者の収入や資産、職歴などが詳細に確認されることが予想されます。これらの情報をもとに、申請者が貸付金を返済する能力があるかどうかを判断します。
連帯保証人を設定するメリット
連帯保証人を設定することには、いくつかのメリットがあります。まず、審査がスムーズに進行する可能性が高まります。連帯保証人がいることで、返済の保証が強化されるため、金融機関も安心して貸付を行うことができます。また、連帯保証人がいることで、より好条件の貸付を受けることができることも考えられます。
連帯保証人がいない場合の注意点
連帯保証人がいない場合、申請者自身の信用が重視されるため、過去の金融取引の履歴や現在の経済状況が詳しく確認されます。特に、過去に返済の遅延や延滞があった場合、審査に通りにくくなる可能性があります。そのため、申請前に信用情報を確認し、必要な場合は改善する努力をすることが望ましいです。
貸付金の返済が困難になった場合の対処法
返済が困難になった場合、まずは早急に貸付金の窓口に連絡することが大切です。返済計画の見直しや返済期間の延長などの対応が考えられます。また、返済困難の原因や現在の生活状況を詳しく伝えることで、より適切な対応を受けることができます。
返済計画の見直し
返済が困難になった際、最初にすることは返済計画の見直しです。月々の返済額を少なくすることで、一時的な返済の負担を軽減することができます。具体的には、返済期間を延ばすことで月々の返済額を減少させる方法が考えられます。
返済期間の延長
返済期間を延長することで、短期間の返済負担を軽減することができます。ただし返済期間が延長されると、長期的には返済総額が増加する可能性があるため、その点を考慮する必要があります。
返済困難の原因の共有
返済が困難になった原因を貸付金の窓口に正確に伝えることで、最も適切な対応を受けることができます。例えば、収入が減少した、病気やケガで働けなくなったなど、具体的な状況を詳細に説明することが望ましいでしょう。
再度の返済計画の確認
返済計画を見直した後、再度その計画を確認することが大切です。新しい返済計画に基づいて、今後の返済がスムーズに行えるかどうかを検討し、必要に応じてさらなる調整を行うことが考えられます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金の実際の利用事例

母子父子寡婦福祉資金貸付金の具体的な利用事例を知ることで、どのような場面でこの制度を活用できるのか、また、どのような効果やメリットが得られるのかを理解することができます。
生活資金としての利用事例
生活資金としての利用は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の主な利用目的の一つです。例えば、子供の学費や医療費、日常の生活費など、さまざまな出費に対応するためにこの制度を利用できます。収入が不安定な家庭や、急な出費が発生した場合には、この制度を活用することで、生活の安定を保つことができます。
子供の学費に対する支援
教育費は家計にとって大きな負担です。入学金や授業料、教材費など、学校教育にはさまざまな費用がかかりますが、母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用することでこれらの教育費をカバーし、子供の学びの機会を確保することができます。
医療費の補填
病気や怪我は予期せずに発生します。また高額な医療費が突如として家計に負担となることもあります。この制度を利用することで、医療費の支払いを行い、家庭の経済的な安定を維持することができます。
日常の生活費の確保
収入が不安定な家庭では、日常の生活費の確保も難しいことがあります。食費や光熱費、交通費など、日常生活を送るための基本的な出費に困ることも考えられます。母子父子寡婦福祉資金貸付金を活用することで、日常の生活を安定させる手段として利用することができます。
急な出費への対応
家電の故障や車の修理など、急な出費は誰にでも発生します。予期せぬ出費により、家計が圧迫されることを防ぐために、この制度を利用して資金を確保することができます。
修学資金としての利用事例
子供の教育費は、多くの家庭にとって大きな負担となります。中学、高校、大学と進学するにつれて教育費は増え、負担はどんどん大きくなります。母子父子寡婦福祉資金貸付金を修学資金として利用することで、子供の進学を支援することができます。
中学生の教育費
中学校に進学する際、制服や教材、遠足や修学旅行などの費用が発生し、家計にとって一時的ながらも大きな出費となります。母子父子寡婦福祉資金貸付金を活用することで、これらの費用をカバーし、子供の中学生活を充実させることができます。
高校生の教育費の特徴
高校に進学すると中学校よりも教育費が増加します。入学金や授業料、部活動の費用など、さまざまな出費が考えられます。この制度を利用することで、高校生活をスムーズに進めるための資金を確保することができます。
大学生の教育費とその対策
大学に進学する際の教育費は、特に高額となることが多いです。学費や住居費、生活費など、多岐にわたる出費が必要となります。母子父子寡婦福祉資金貸付金を修学資金として利用することで、大学生活を安心して送ることができます。
進学を考える家庭の取り組み
子供の進学を考える家庭は、早い段階からの資金計画が求められます。教育費の増加を見越して、適切な資金の準備や計画を立てることで、子供の学業を無理なく支援することができます。
住宅資金としての利用事例
新しい家を建てる、または既存の家をリフォームする際の資金として、母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用することもできます。住宅の購入やリフォームは大きな費用がかかるため、この制度を活用することで住宅の購入やリフォームをスムーズに進めることができます。また、住環境の改善や、安全な住まいを手に入れるための手段としても利用されています。
新築住宅の購入について
新築住宅の購入は多くの家庭にとって、一生に一度の大きな出費でしょう。土地の購入から建築費用、内装や設備の費用など、さまざまな経費が発生します。母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用することで、これらの費用を効果的にカバーし、理想の住まいを実現することができます。
既存住宅のリフォームと改築
既存の住宅をより快適に、または安全にするためのリフォームや改築も、多額の費用が必要となることが多いです。特に、古い住宅の耐震補強やバリアフリー化など、大規模なリフォームを行う場合、資金の準備が欠かせません。この制度を活用することで、リフォームや改築を計画的に進めることができます。
住環境の改善のための取り組み
住環境の改善は、家族の健康や生活の質を向上させるために重要です。例えば、結露対策や断熱改善、換気設備の導入など、住環境を快適にするための取り組みが考えられます。母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用することで、これらの取り組みを実現するための資金を確保することができます。
安全な住まいの実現
地震や台風などの自然災害から家族を守るための住宅の安全性は、日本において非常に重要です。耐震性や耐風性を高めるための工事や、防災設備の導入など、安全な住まいを実現するための取り組みが必要です。この制度を活用することで、安全な住まいを手に入れるための資金計画を立てることができます。
