子供の養育費、中でも教育費は毎年増えていっています。中学から高校、高校から大学といったように、進学で教育費は一気に増えることもありますが、学校の授業料などは確実に上昇しています。
一般的な家庭でもい、教育費は生活費の中でも大きな負担ですが、これが母子家庭になると、収入に対する教育費の割合はかなりのものになり、場合によっては普段の生活を大きく圧迫する原因にもなっています。
生活のための必要経費である、衣食住が最優先になるのは当然ですが、そうなると教育費はどうしても後回しになりがちです。
しかし、教育はすぐに結果は見えませんが、子供の将来の選択に大きく影響を与えます。子供が思うような教育が受けられないと、将来も不安になりますよね。
そんな時、奨学金や自治体が実施する母子父子寡婦福祉資金の貸付金は、大きな助けとなります。
奨学金は昔からあり、存在を知っている人は多いと思います。母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭の方なら一度は聞いたことがあるかもしれません。
どちらも誰でも利用できるというわけではなく、世帯の収入が決められた金額以下といった条件があります。その条件に当てはまらないと利用することはできません。
また、意外と見落とされがちなのは、奨学金と母子父子寡婦福祉資金、この2つを同時に利用、つまり併用できるのか、です。
子供が目指す学校に行くためには、奨学金、あるいは母子父子寡婦福祉資金単独では足りないので、できれば両方を利用したい、というケースも出てくるでしょう。
そしてその実態は、自治体によって可能であったりできなかったりと、様々です。
そこでここでは、奨学金と母子父子寡婦福祉資金を同時に利用、併用する場合について、詳しく見ていきます。
母子父子寡婦福祉資金と奨学金の違いは?

奨学金
民間、あるいは自治体などが運営する団体が学生に提供する教育資金です。
返済が必要な貸与型奨学金と、返済が不要な給付型奨学金があります。後者の代表的な団体が、JASS(日本学生支援機構)です。
支給額は団体によって様々で、利率、償還期間も変わってきます。
利用の条件としては、世帯の収入、世帯構成(ひとり親世帯かどうか等)、障害の有無などがあり、毎月決まった金額を支給か、授業料等かかった実費の支給を受けることになります。
母子父子寡婦福祉資金
母子父子寡婦福祉資金は、内閣府男女共同参画局が定める貸付金制度で、利用できるのは、20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等となっています。
母子家庭では20歳未満の子供のいる方が対象になる、ということですよね。
この貸付金が使える対象としては、
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金
- 技能取得資金
- 修業資金
- 就職支度金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 就学支度資金
- 結婚資金
があり、多岐に渡っていますが、このなかで子供の教育費として使えるのが「修学資金」です。
修学費用では、利率は無利子で償還期間は20年となっています。支給額は学校の種類によって変わりますが、具体的な支給額は後述します。
また、内閣府、つまり国が定める貸付金なので、住む場所によって条件や支給額が変わる、といったことはありません。
では、母子父子寡婦福祉資金と奨学金は併用できるのでしょうか?
母子父子寡婦福祉資金と奨学金の申請手続き

母子父子寡婦福祉資金や奨学金を利用するためには、決められた申請手続きが必要となります。申請手続きは多くの人にとって初めての経験であり、どのような手順を踏むべきか、どのような書類が必要かなど、多くの疑問が浮かぶことでしょう。ここでは、申請の流れや必要書類、注意点などを詳しく説明していきます。
まず、自治体や学校の窓口で申請書を入手することから始まります。申請書には、個人情報や家族構成、収入状況などの詳細な情報を記入する必要があります。所得証明書や住民票などの公的な書類を添付することが求められる場合もあります。
これらの書類は、申請者の経済状況や家族構成を確認するためのものであり、正確に記入することが重要です。正確な情報提供は、適切なサポートを受けるための鍵となります。
申請の流れと必要書類
申請の流れは、まず自治体や学校の窓口で申請書を入手することから始まります。この申請書は、福祉資金や奨学金の申請に必要な基本的なフォームとなっており、申請者の基本情報を始め、家族の構成や収入、資産状況などの詳細を記入する欄が設けられています。
次に、申請書に記載された内容を証明するための書類を準備します。所得証明書は、申請者の年収や所得を証明するためのもので、勤務先や市役所で取得することができます。住民票は、現在の住所や家族構成を証明するための書類となります。これらの書類は申請の審査において非常に重要な役割を果たしますので、正確かつ最新のものを提出することが求められます。
書類が全て揃ったら、指定された場所、たとえば自治体の福祉課や学校の学務課などに提出します。提出後、専門の担当者による審査が行われます。この審査では、申請者の経済状況や家族構成、学業の状況などが詳細に検討され、福祉資金や奨学金の受給資格があるかどうかが判断されます。
審査の結果は、数週間から数ヶ月後に通知されることが一般的です。通知は書面で行われ、受給資格がある場合はその詳細や受給額、返済方法などが記載されています。また、申請時には面接が設けられる場合もあります。面接では、申請書や提出書類だけでは伝えきれない申請者の状況や希望を直接伝える機会となりますので、事前にしっかりと準備をしておくようにします。
申請時の詳細な注意点とよくある質問
申請時の手続きは煩雑であり、多くの注意点が伴います。申請書の記入に関しては、一つ一つの項目を慎重に読み、正確な情報を提供することが求められます。特に金額や日付の記入は、数字の間違いが非常に起こりやすい部分です。このような基本的なミスを避けるためには、記入後に何度も確認を行うことが大切です。
申請に必要な書類は、申請書だけでなく、所得証明書や住民票などの公的な書類も含まれます。これらの書類は申請の審査において非常に重要な役割を果たします。もし書類が不足していると、基本的に申請は受理されません。事前に必要な書類のリストをチェックし、全ての書類を揃えてから申請することが望ましいです。
申請の締め切り日は自治体や学校によって異なります。締め切り日を逃すと次の申請期間まで待たなければならないため、日程をしっかりと確認し、余裕を持って申請を行うことが大切です。
よくある質問の中で、「所得証明書の取得方法は?」というものがあります。所得証明書は、勤務先の人事部や経理部、または市役所や区役所の窓口で申請・取得することができます。取得には、一定の手数料がかかる場合がありますので、事前に確認しておくことが推奨されます。
また、「申請の際の面接はどのような内容になるのか?」という質問に関しては、面接では申請者の経済状況や学業の状況、家族構成などの詳細を深堀りすることが目的となります。面接官は、申請者の実際の状況をより正確に把握するための質問を行いますので、正直かつ具体的に回答することが求められます。
申請後の手続きと変更手続き
申請が正式に受理されると、受給決定通知が申請者のもとに送られてきます。この通知は非常に重要で、奨学金や福祉資金の受給に関する全ての詳細情報が記載されています。具体的には、受給額の詳細、返済の方法や期間、返済の際の利息率など、今後の手続きや返済に関する情報が網羅されています。
受給決定通知を受け取った後、指定された銀行口座に資金が振り込まれます。この際、口座の名義や番号が正確であることを確認することが重要です。間違った情報が提供されていると、資金の振り込みが遅れるなどの問題が起こるからです。
申請後に生じた変更事項に関しては、迅速な対応が必要です。住所の変更、学校の転校や卒業、勤務先の変更など、これらの情報が変わった場合は変更手続きを行う必要があります。この手続きは、受給決定通知に記載されている方法や自治体や学校の窓口での指示に従って行います。変更手続きを怠った場合、奨学金や福祉資金の受給が一時停止されるリスクがあるため、変更があった際は速やかに手続きを行う必要があります。
変更手続きに関する具体的な方法や必要な書類は、自治体や学校によって異なるため、手続きを行う前に必要な書類や手続きの流れをしっかりと確認しておくことが大切です。また変更手続きの際には、新しい情報を証明するための書類、例えば新しい住民票や学生証、雇用証明書などが必要となりますので、事前に準備しておきましょう。
母子父子寡婦福祉資金と奨学金は併用できる?

母子父子寡婦福祉資金と貸与型奨学金の併用の可否は、自治体によって取り扱いが異なります。
例えば、埼玉県の場合は日本学生支援機構から貸与型奨学金を受けている場合、母子父子寡婦福祉資金の修学資金の貸付限度額を上限として差額を借りる事が出来ます。
一方、大阪府の場合、民間の奨学金を含め、貸付金との併用は認められていません。
このように、自治体によって母子父子寡婦福祉資金と奨学金は併用できるかどうか変わるのが、現在の実情です。
そのため、ご自身が住む地域の自治体に、併用できるのかどうか確認する必要があります。
母子父子寡婦福祉資金と併用できる奨学金は?

文部科学省による教育制度改革の一環として、令和2年4月から、高等教育の修学支援新制度が始まりました。
高等教育の修学支援新制度
文部科学省のホームページには、次のように解説されています。
令和2年4月から実施の高等教育の修学支援新制度の概要
政府は、平成29年12月の「新しい経済政策パッケージ」、平成30年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2018(いわゆる骨太の方針)」において、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金の大幅拡充により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する方針を決定しました。(令和元年10月の消費税率10%への引上げによる増収分の一部を財源としています。)
この新たな支援措置は、令和2年4月から実施しています。
高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金を受給しながら、授業料・入学金の免除や減免を受けられるという制度で、世帯収入と学習意欲が要件となります。
そしてこの修学支援制度では、奨学金は母子父子寡婦福祉資金の「修学資金」と併用可能になっています。
併用時の優先度
厚労省が自治体に向けて出した「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の運用について」という通達に、具体的な運用方法が記載されています。
この中で、母子父子寡婦福祉資金の修学資金の貸付金の希望があった場合、先に修学支援制度を活用するように促す事が求められています。
つまり、優先順位は修学支援制度を利用した給付型奨学金や学費の減免の方が上となります。
借入金額上限について
母子父子寡婦福祉資金の「修学資金」には、貸付金額上限が存在します。修学支援制度と併用する場合、修学支援制度よる減免・免除された金額と奨学金の給付額が、貸与金上限から差し引かれる事になります。
貸付上限は、最も金額が大きくなる私立の自宅外通学の場合の月額で、以下の通りとなります。
- 高校、専修学校(高等課程):52,500円
- 高等専門学校[1~3年]:52,500円
- 高等専門学校[4~5年]:115,000円
- 専修学校(専門課程): 126,500円
- 短期大学:131,000円
- 大学:146,000円
- 大学院(修士課程):132,000円
- 大学院(博士課程):183,000円
- 専修学校(一般課程):51,000円
同条件で修学支援制度を利用した場合、授業料減免が年間約70万円で月額にすると58,300円ほど、奨学金が年間75,800円となるため、合計で134,100円の支援が受けられます。
従って、貸付を受けられる金額は、
11,900円(実際の貸付金)=146,000円(貸付金上限)-134,100円(修学支援制度支援額)
11,900円まで貸付を受ける事が可能となります。
尚、貸付上限は、さかのぼって適用される場合があります。
例えば、修学支援制度による入学金などの減免が後から決まった場合、引き下げられた貸付限度額が、実際の貸付額よりも少なくなる場合があります。
そしてこの多く借りすぎていた貸付額は、すぐに返還する必要があります。
但し、生活に支障が出ないよう考慮する必要があるため、返還方法として毎月の貸与金から相殺する方法が例示されています。
給付型奨学金の利用中から切り替える
現在給付型奨学金を受給中の場合、条件を満たせば修学支援制度に切り替える事が可能です。
また、既に母子父子寡婦福祉資金の「修学資金」の貸付を受けている時も、修学支援制度を新たに利用開始する事も可能です。こちらも、切り替える途中で余分に受け取った貸付金が出た場合は、返還が必要となります。
母子父子寡婦福祉資金と奨学金の返済方法

母子父子寡婦福祉資金や奨学金の返済は、返済の方法やスケジュール、注意点などを理解し、計画的に返済を進めることが大切です。返済の基本的な流れは、受給決定通知に記載されている返済スケジュールに従い、指定された金額を指定された期間内に返済することとなります。返済方法には、口座振替や郵便局での支払いなど、いくつかの方法が考えられます。
返済の詳細な流れとスケジュールのポイント
返済に関する手続きは受給決定通知を基に行われます。この通知には返済に関する全ての詳細情報が明記されており、返済者はこの通知をもとに返済スケジュールを確認する必要があります。具体的には、返済の開始日、終了日、返済の頻度(例:月1回)、返済金額などが詳細に記載されています。
返済開始日が訪れると、返済者は指定された金額を返済する義務が生じます。この際、返済方法は大きく分けて二つの方法が考えられます。一つ目は口座振替による返済です。口座振替を選択した場合、返済者は特に何もすることなく、指定された日に自動的に銀行口座から返済金額が引き落とされます。この方法は毎月の返済を忘れるリスクが低く、手間もかからないため、多くの返済者に選ばれる方法です。
二つ目の方法は、郵便局を利用した返済です。この方法を選択した場合、返済者は毎月指定された日に自ら郵便局に足を運び、返済金額を支払う必要があります。この方法は口座振替と比べて手間がかかる一方、自らの手で返済を行うことで、返済の意識を高めることができるというメリットがあります。
いずれの返済方法を選択するにしても返済スケジュールを守ることが非常に重要です。返済を怠った場合、遅延損害金が発生する可能性がありますので、返済日を忘れないようにカレンダーやスマートフォンのアラーム機能などを活用して、返済を確実に行うよう心がけましょう。
返済時の注意点とよくある質問
返済時には、いくつかの注意点が存在します。まず、返済金額や返済日を確実に守ることが大切です。返済金額や返済日は、奨学金や福祉資金の受給決定通知に明記されており、これらの日程や金額を守ることが基本的な義務となります。返済を怠ると遅延損害金が発生する可能性があります。また、返済が困難な場合は、早めに相談窓口に連絡する必要があります。
経済的な理由や突発的な出来事などで返済が困難になった場合、すぐに奨学金や福祉資金の提供機関の相談窓口に連絡を取りましょう。返済計画の再検討や一時的な返済猶予が受けられたり、返済支援策などの選択肢を提案してもらえることもあります。
返済に関するよくある質問の中で、「返済が困難な場合の対応は?」というものがあります。この質問に対する答えは、提供機関や自治体、学校によって異なる場合がありますが、一般的には返済計画の再設定や一時的な返済猶予などの対応が考えられます。
「返済金額の変更は可能か?」という質問に関しては、返済者の経済状況の変化や特別な事情が認められる場合、一定の条件下で返済金額の変更が許可されることがあります。しかし、このような変更を希望する場合は、詳細な手続きや条件を提供機関の窓口で確認し、必要な書類を提出することが必要となります。
返済の遅延や困難時の具体的な対応策とその手続き
どんなに周到に準備、計画していたとしても、予想していなかったことが起こったなどで返済が遅れたり返済できなくなることがあります。もしそうなってしまった時は、適切な対応を取る必要があります。
返済が遅れると、遅延損害金を追加して支払わなくてはなりません。遅延損害金は返済金額に応じて計算されるため、返済が遅れることが予想される場合は、事前に関連する機関や窓口にその旨を伝えることが重要です。理由にもよりますが、事前の連絡により遅延損害金の免除や減額の対応が受けられる場合もあるからです。
返済が困難な状況になった場合、その原因や背景の説明が求められます。例えば、失業や病気、家族の事情など、返済困難の具体的な理由を関連する機関に伝えることで、返済計画の再検討や返済額の減額、返済期間の延長などの対応策が提案されることがあります。
そして返済困難の状況においても、定期的に関連する機関とのコミュニケーションを維持することが大切です。定期的な情報提供や相談を行うことで、返済計画の見直しや支援策の提案など、より柔軟な対応が受けられる可能性が高まります。
返済の遅延や困難時の対応策を利用する際は、必要な書類や証明書を用意する必要があります。返済困難の理由や状況を証明するためのものであり、返済計画の再検討や支援策の提案を受けるための重要な手続きとなります。そのため、必要な書類を事前に確認し、不足なく提出しなくてはなりません。
母子父子寡婦福祉資金と奨学金の実際の活用事例

母子父子寡婦福祉資金や奨学金は、多くの家庭で実際に利用されています。これらの資金や奨学金を利用することで、経済的な困難を乗り越え、学業や生活を支えることができるケースが多数報告されています。
母子家庭での成功事例
母子家庭での経済的な困難は多くの家庭で共通の悩みとなっています。Aさんのケースもその一例です。突然の夫の死により、子供2人を育てる母としての役割だけでなく、家計の管理も一人で行うこととなったAさんは、多くのプレッシャーと向き合うこととなりました。
特に子供たちの教育費は大きな負担となっていました。中学生の長男と小学生の次男の学業を継続させるためには、安定した収入と教育資金が必要でした。しかし夫の死後、Aさんの収入だけでは家計が厳しく、教育資金の捻出が難しい状況でした。
そんな中、友人から母子父子寡婦福祉資金の制度を教えてもらい、Aさんはこの制度を利用することを決意しました。自治体の窓口での相談を経て、必要な書類を提出。審査を経て福祉資金の受給が決定しました。この資金により、Aさんは子供たちの学業を継続させることができました。
さらに、長男が高校を卒業し大学に進学する際には、奨学金の制度も利用。大学の学費を賄うことができ、長男も無事に大学生活をスタートさせることができました。Aさんはこれらの制度を上手く活用することで、子供たちに良い教育環境を提供することができました。
現在、Aさんの家庭は経済的にも安定してきており、次男も中学を卒業し高校に進学。Aさんは多くの困難を乗り越え、子供たちに明るい未来を提供することができました。
寡婦家庭での成功事例
夫の急逝により、3人の子供を一人で育てることとなったCさんは、経済的な困難に立ち向かうこととなりました。
夫の収入が途絶え、家計は一気に厳しくなりました。特に3人の子供たちの教育費や日常の生活費は、Cさんの収入だけでは賄いきれない状況でした。そこでまずCさんは地域の福祉センターや自治体の窓口を訪れ、寡婦家庭を支援するための情報を収集しました。
その結果、寡婦家庭を支援するための福祉資金や奨学金の制度を知ることができました。これらの制度を活用することで、Cさんは子供たちの教育や生活を支えることができました。長女が大学に進学する際、奨学金の制度を利用して学費を賄うことができました。
地域の福祉センターでは、寡婦家庭を支援するための様々なワークショップやセミナーも開催されており、Cさんはこれらの活動を通じて、同じような状況にある他の寡婦たちとの交流の場を持つことができました。このような交流を通じて、Cさんは多くの情報やアドバイスを得ることができ、子供たちの教育や生活をより良くするためのヒントを得ることができました。
現在、Cさんの家庭は経済的にも安定してきており、子供たちもそれぞれの道を歩んでいます。Cさんは、自治体や地域の支援を受けることで子供たちに良い環境を提供することができたと感謝しています。
母子父子寡婦福祉資金と奨学金、制度の改正には要注意
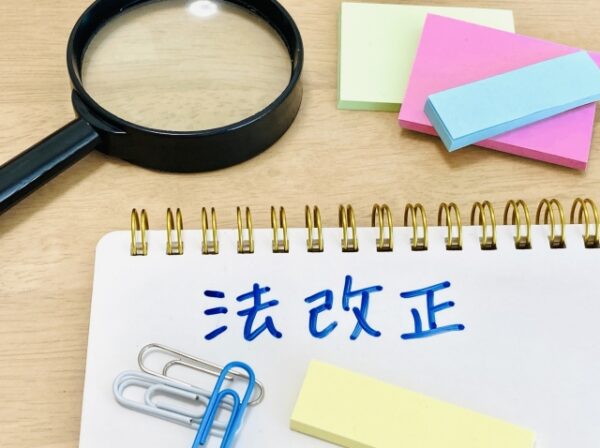
子供の教育に限らず、公的な制度は便利で大きな助けになりますが、しばしば改定が行われます。必要になった時に探し始めても、見つけ出すのはなかなか難しいものです。
自分の利用している制度に興味関心を持つ事は大切です。常時とは言わないまでも、年度替わりに確認しておくと、効率よく情報を知る事が出来るでしょう。
探すのがどうしても難しい場合は、信頼出来る行政の担当者を持つなど、自分に合った形で情報収集を行い、制度を有効に活用しましょう。
