様々な事情で母子家庭となった時、今まで配偶者の被扶養者として免除されていた様々な料金を自分で支払う必要が出てきます。
そういった料金の中でも、地域や年度で変わるため、今ひとついくらになるかなかなか把握が難しいのが国民健康保険料でしょう。
母親であるあなた自身が元々会社で働いている場合は、その会社が加入している健康保険の被保険者になりますが、国民健康保険というのは、他の健康保険から外れた時には即座に加入となる隙間を埋める保険です。
また会社が加入している健康保険では、支払う保険料の半分は会社が負担してくれますが、会社で働いていない場合は、国民健康保険料の支払いは全額自己負担になります。
母子家庭になる前から会社で働いていて母子家庭になってからもそのまま、という方であれば、自己負担は半分ですが、母子家庭になる前は専業主婦という方は、保険料全額を自分で払わなくてはいけなくなります。
さらに、国民健康保険は民間の保険のように個人が任意で加入や脱退するものではなく、国民全員が加入することになっています。「今は元気で滅多に病院に行かないから、10年後から入ります」というような事はできません。
母子家庭になり一時的に収入がなくなる、あるいは収入が減る、という方は少なくないでしょう。加入しないといけない国民健康保険、その国民健康保険料はいくら必要なのか、とても心配になりますよね。
ここでは、母子家庭になると国民健康保険料はいくら払うことになるのか、見ていきます。
母子家庭の国民健康保険料の基本情報

母子家庭は、経済的な困難を抱える家庭が多いとされています。そのため、国や自治体からのさまざまな支援が考えられています。中でも、医療費の補助としての国民健康保険料の特典は、多くの母子家庭にとって非常に重要です。
国民健康保険は日本の全国民を対象とした健康保険制度の一つであり、この保険制度は、医療費の一部を補助することを目的としています。保険料は収入や家族構成に応じて計算されるため、母子家庭の場合、特定の条件を満たすと保険料の減額や免除が受けられる場合があります。
このような制度は、母子家庭が医療サービスを受けやすくするためのものであり、経済的な負担を軽減するためのものです。
国民健康保険料の基本的な仕組み
国民健康保険の成立背景
国民健康保険制度は、1947年に制定された国民健康保険法に基づき設立されました。この制度の目的は、非被用者(主に自営業者やフリーランスなど)を対象として、医療サービスを受ける際の経済的な負担を軽減することです。
保険料の計算基準
国民健康保険の保険料は、所得税の課税標準に基づいて計算されます。具体的には、前年度の所得額や家族構成、世帯の人数などが考慮されます。また、所得が一定の額を超えると、保険料の額が増加する仕組みとなっています。
減額や免除の制度について
国民健康保険料の減額や免除制度は、所得が一定の基準を下回る場合や、65歳以上の高齢者、障害者など、特定の条件を満たす人々が対象となります。この制度の詳細や適用基準は、自治体によって異なるため、住民が所属する自治体のホームページや窓口で確認する必要があります。
自治体による違い
国民健康保険の制度や保険料の計算方法は、自治体によって異なる場合があります。これは、各自治体が独自の医療政策や財政状況に応じて、国民健康保険の制度を適切に運用しているためです。そのため、自分の住む地域の制度や保険料の計算方法を正確に理解することが重要です。
母子家庭の国民健康保険料の特徴
母子家庭の定義と背景
母子家庭は、父親がいない家庭を指し、多くの場合、経済的に厳しい状況にあります。日本の社会保障制度は、このような家庭の経済的困難を考慮し、さまざまな支援策を講じています。
保険料の減額制度
母子家庭は、所得に応じて国民健康保険料が減額される制度の対象となることが多いです。具体的には、所得が一定の基準を下回る場合、保険料の額が減少します。この基準は自治体ごとに異なるため、具体的な額や条件は住民が所属する自治体で確認する必要があります。
保険料の免除制度
さらに、特定の条件を満たす母子家庭は、国民健康保険料の免除を受けることができます。この制度は、所得が非常に低い場合や、特定の障害や疾病を持つ家庭に適用されることが多いです。
子供の数や年齢に応じた特典
母子家庭の場合、子供の数や年齢に応じて、さらなる減額や免除の特典が受けられる場合があります。例えば、18歳未満の子供が複数いる場合、保険料の額がさらに減少する自治体が存在します。
自治体によるサポート
多くの自治体は、母子家庭を支援するための独自の制度やサービスを提供しています。これには、医療費の一部補助や、子供の医療費の全額補助などが含まれます。これらのサポートは、母子家庭が医療サービスを受ける際の経済的な負担を大きく軽減するものであり、多くの家庭にとって大きな支えとなっています。
母子家庭の場合、子供の数や年齢に応じてさらなる減額や免除が受けられる場合があります。このような特典は、母子家庭が医療サービスを受けやすくするためのものであり、経済的な困難を乗り越えるための大きな支えとなっています。
母子家庭の国民健康保険料はどのようにして決まる?
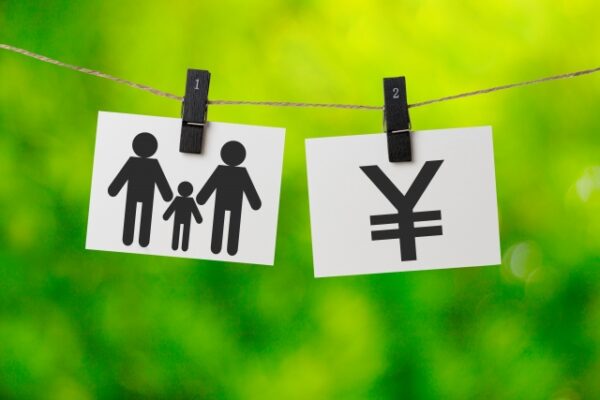
国民健康保険料と一言で言っても、実際にはいくつかの要素を元に計算されることになっています。
一般的に言われる国民健康保険料は、厚生労働省のHPでは、
「世帯単位で算定し、世帯の被保険者ごとに応益分・応能分の各種類を計算し、それらを合計したもの」
と定義されています。
そして国民健康保険料の賦課方法は、「受益に応じた応益割、負担能力に応じた応能割があり、その各々に2種類の賦課方法がある」となっています。
| 種類 | 賦課方法 | |
| 応益割 | 均等割 | 世帯に属する被保険者数に応じて賦課(子供を含む) |
| 平等割 | 世帯ごとに賦課 | |
| 応能割 | 所得割 | 世帯に所属する被保険者の所得に応じて賦課 |
| 資産割 | 世帯に所属する被保険者の固定資産額に応じて賦課 |
この4種類がすべて足し合わされるのではなく、各市町村の判断で、所得割+均等割、所得割+均等割+平等割、所得割+資産割+均等割+平等割のいずれかを選択できるようになっています。
これは言い換えると、国民健康保険料は人数と世帯の分、必ず発生することになるので、もし収入がゼロだったとしても発生します。母子家庭になる前は専業主婦で収入がない、という方には厳しい話ですよね。
そこで、母子家庭である事のみを理由とした軽減はありませんが、低所得になった事で国民健康保険料の減額制度が適用される場合があります。
母子家庭が利用できる国民健康保険料の減額制度とは?

国民健康保険料の減額制度
母子家庭が利用できる国民健康保険料の減額制度というのは、法令により定められた所得基準を下回る世帯に対し、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割又は2割を減額する、という制度です。
所得と減額の割合は次のようになっています。(厚生労働省HPより抜粋)
| 減額割合 | 対象者の要件(令和3年) |
| 7割 | 43万円以下 |
| 5割 | 43万円+(被保険者数)x28.5万円以下 |
| 2割 | 43万円+(被保険者数)x52万円以下 |
母子家庭でこの要件に該当する方であれば、減額制度の利用が可能です。
国民健康保険料を試算
国民健康保険は自治体が運営しているため、住んでいる地域や年度によって国民健康保険料の具体的な金額は変動します。
ここでは令和4年度の札幌市を例に、母1人、子1人の母子家庭、所得85万円(給与収入140万円)で、基本的な国民建国保険料がいくらになるか、試算してみましょう。
(1)均等割、平等割りの軽減
低所得世帯による軽減制度で、所得43万円以下で70%の減額、それより多い場合も、子供の数等により50%か20%の減額が適用されます。
例の所得の場合は50%の適用となります。
以下の均等割・平均割の単価は、50%適用後です。
(2)所得割用の所得額:42万円
給与収入:140万円
給与所得控除:55万円
基礎控除(※住民税):43万円
140万円 – 55万円 – 43万円 = 42万円
所得税の基礎控除48万円とは異なります
(3)内訳の計算
(A)医療分保険料:68,330円(10円未満切捨)
所得割:42万×8.63%=36,246円
均等割:8,600円×2人=17,200円
平等割:14,885円×1世帯=14,885円
(B)支援金分保険料:23,040円(10円未満切捨)
所得割:42万×2.93%=12,306円
均等割:2,880円×2人=5,760円
平等割:4,980円×1世帯=4,980円
(C)介護保険料:16,530円(10円未満切捨)
・所得割:42万×2.44%=10,248円
・均等割:2,655円×1人(※)=2,655円
・平等割:3,635円×1世帯=3,635円
※49~65歳未満のみのため、1名の適用
(4)合計額:10,790円(年額)
(A)+(B)+(C)=10,790円(年額)
子供一人の母子家庭では、国民健康保険料は10,790円となりました。
なお札幌市の場合、公式サイトに金額の早見表があるため、細かい計算をせずに自分の給与から自分の国民健康保険料がいくらかを知る事が可能です。
他にも、地域まで指定して試算が行えるウェブサイトもありますので、母子家庭の方はぜひ参考にして下さい。
母子家庭の国民健康保険料の節約方法

母子家庭は、一つの収入源で家計を支えることが多いため、経済的な困難が増えることが考えられます。そのため、国民健康保険料の節約は、家計の安定に大きく寄与します。
減額制度や免除制度の活用
国民健康保険料の減額制度とその基準
国民健康保険料の減額制度は、所得が一定の基準を下回る場合に適用される制度です。この基準は、各自治体によって設定されており、所得税の課税標準や家族構成、子供の数や年齢などが考慮されることが一般的です。減額の具体的な割合や金額は、自治体によって異なります。
国民健康保険料の免除制度とその基準
免除制度は、所得が非常に低い場合や、特定の障害や疾病を持つ家庭、または特定の生活困難状況にある家庭を対象としています。免除の適用を受けるためには、所在地の市町村役場や区役所に申請する必要があります。免除の基準も自治体ごとに異なるため、具体的な条件や手続きは自治体の情報を参照する必要があります。
母子家庭における特例
母子家庭は、一つの収入源で家計を支えることが多いため、経済的な困難が増えることが考えられます。そのため、多くの自治体では、母子家庭を対象とした特例措置を設けています。これにより、所得の基準が緩和される場合や、子供の数に応じてさらなる減額や免除が受けられる場合があります。
自治体の情報提供
各自治体は、国民健康保険料の減額や免除制度に関する情報をホームページやパンフレットで提供しています。また、窓口では、専門の職員が詳しい説明や相談に応じてくれます。これらの情報を活用することで、自身の状況に合った支援を受けることができます。
地域や自治体によるサポート
各地域や自治体には、母子家庭を支援するためのさまざまなサポートが考えられています。具体的なサポート内容や利用方法は、各自治体のホームページや窓口で確認することができます。
子育て支援サービス
多くの自治体では、母子家庭を対象とした子育て支援サービスを提供しています。これには、子育て相談や子育て支援センターの利用、子どもの健康診断や予防接種の補助、子どもの学習支援などが含まれます。
住宅支援
経済的な困難から適切な住居を確保できない母子家庭に対して、公営住宅の優先的な提供や住宅補助金の支給などのサポートが行われています。
教育支援
学校の給食費の減免や、学用品の補助、学習塾や習い事の補助など、教育に関する経済的な負担を軽減するためのサポートが各自治体で行われています。
雇用支援
母子家庭の母親が就職や再就職を希望する場合、職業訓練や就職相談、求人情報の提供などのサポートが行われています。
情報提供
各自治体は、母子家庭向けのサポート情報をホームページやパンフレット、情報誌などで定期的に提供しています。これにより、最新の支援情報やイベント、講座などの情報を得ることができます。
母子家庭が国民健康保険料を支払う際の手続き

母子家庭となった場合、国民健康保険料の支払いは避けて通れない課題となります。しかし、その手続きは一見複雑に見えるかもしれません。ここでは、その手続きをスムーズに進めるための基本的な情報を解説します。
手続きの流れ
母子家庭が国民健康保険料を支払う際の手続きは、一見複雑に見えるかもしれません。しかし、手続きの流れを理解すれば、スムーズに進めることができます。ここでは、その詳細な手続きの流れを説明します。
まず、国民健康保険料の支払いは、母子家庭の主である母親が行うことになります。そのため、母親が国民健康保険の被保険者となり、保険料を支払う責任があります。この保険料は、母親の収入や家庭の状況によって変動します。
次に、国民健康保険料の支払いは、毎年定められた期間内に行う必要があります。支払いは、通常、市町村の窓口や指定された金融機関で行います。また、インターネットバンキングやクレジットカードを利用した支払いも可能な場合があります。
さらに、国民健康保険料の支払いが完了したら、その証明となる領収書を保管しておくことが重要です。万が一、支払いの確認が必要になった場合に備えて、領収書は大切に保管してください。
支払いの準備
国民健康保険料の支払いを行う前に、いくつかの準備をする必要があります。まず、市町村から送られてくる国民健康保険料の請求書を確認します。この請求書には、支払い期限や支払い方法、支払い額などが記載されています。
また、支払いを行うための手段を準備します。支払いは、通常、市町村の窓口や指定された金融機関で行います。しかし、インターネットバンキングやクレジットカードを利用した支払いも可能な場合があります。そのため、自分に合った支払い方法を選び、準備をしておくことが重要です。
支払いの実行
準備が整ったら、次に国民健康保険料の支払いを行います。請求書に記載されている期限内に、指定された方法で支払いを行います。支払いが完了したら、その証明となる領収書を受け取ります。
領収書は、後々の確認のために保管しておくことをおすすめします。万が一、支払いの確認が必要になった場合に備えて、領収書は大切に保管してください。
必要な書類
母子家庭が国民健康保険料を支払う際には、いくつかの書類が必要になります。これらの書類は、手続きをスムーズに進めるため、また、自身の経済状況を証明するために必要です。ここでは、その詳細な書類について説明します。
まず、国民健康保険料の支払いを行うためには、国民健康保険の被保険者証が必要です。この被保険者証は、国民健康保険に加入していることを証明する書類で、市町村から発行されます。
次に、所得証明書も必要になります。所得証明書は、自身の年収や所得を証明する書類で、市町村や税務署から発行されます。この書類は、国民健康保険料の計算や、減額や免除の申請に必要です。
さらに、母子家庭であることを証明する書類も必要です。例えば、戸籍謄本や戸籍抄本、独身証明書などが該当します。これらの書類は、市町村の窓口で取得することができます。
書類の準備
これらの書類を準備する際には、いくつかのポイントを覚えておくと良いでしょう。まず、各書類は最新のものを用意することが重要です。古い情報が記載された書類は、手続きに支障をきたす可能性があります。
また、書類を取得する際には、手数料が必要な場合があります。そのため、事前に必要な手数料を確認し、準備しておくことをおすすめします。
書類の提出
必要な書類を準備したら、次に市町村の窓口に提出します。書類の提出は、通常、母親が行います。書類を提出した後、市町村からの指示に従って手続きを進めていきます。
なお、書類の提出は、通常、市町村の窓口の営業時間内に行う必要があります。そのため、事前に窓口の営業時間を確認し、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。
母子家庭が国民健康保険料を支払う際に利用できる支援制度

母子家庭が国民健康保険料を支払う際、知っておくべき支援制度があります。これらの制度は、母子家庭の経済的負担を軽減するために設けられています。ここでは、そのような支援制度について詳しく説明します。
国民健康保険料の支払いは、家庭の経済状況によっては大きな負担となることがあります。しかし、母子家庭には、国民健康保険料の減額や免除を受けることができる制度が存在します。これらの制度を利用することで、母子家庭の経済的負担を軽減することが可能です。
これらの支援制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的な条件は、住んでいる市町村により異なるため、詳細は各市町村のホームページや窓口で確認してください。
支援制度の詳細
母子家庭が国民健康保険料を支払う際に利用できる支援制度には、主に減額制度と免除制度があります。
減額制度
母子家庭が国民健康保険料を支払う際に利用できる支援制度の一つに、減額制度があります。この制度は、所得が一定の基準以下の家庭に対して、国民健康保険料の負担を軽減するためのものです。
減額制度の詳細について説明する前に、まずは国民健康保険料がどのように計算されるのかを理解することが重要です。国民健康保険料は、基本的には前年度の所得に基づいて計算されます。そのため、所得が少ない家庭ほど、支払うべき保険料も少なくなります。
しかし、所得が一定の基準以下の家庭に対しては、さらに保険料の減額が適用されることがあります。これが減額制度です。この制度を利用することで、母子家庭は国民健康保険料の負担を大幅に軽減することが可能です。
減額制度の適用基準
減額制度の適用基準は、市町村によって異なることがあります。一般的には、所得が一定の基準以下であること、また、その他の生活状況(例えば、家族構成や住居状況など)が考慮されます。
具体的な基準については、各市町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせることで確認することができます。また、市町村のウェブサイトにも情報が掲載されていることが多いです。
減額制度の申請方法
減額制度を利用するためには、市町村に申請する必要があります。申請には、所得証明書や戸籍謄本などの書類が必要になることがあります。
申請は、通常、母親が行います。申請を行った後、市町村からの指示に従って手続きを進めていきます。
免除制度
国民健康保険料の支払いに困っている母子家庭にとって、免除制度は大きな救いとなるでしょう。この制度は、特定の条件を満たす家庭に対して、国民健康保険料の全額または一部を免除するものです。
免除制度は、生活保護を受けている家庭や所得が一定額以下の家庭など、経済的に困難な状況にある家庭を対象としています。この制度を利用することで、母子家庭は国民健康保険料の負担を大幅に軽減することが可能です。
免除制度の適用基準
免除制度の適用基準は、市町村によって異なることがあります。一般的には、所得が一定の基準以下であること、また、その他の生活状況(例えば、家族構成や住居状況など)が考慮されます。
具体的な基準については、各市町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせることで確認することができます。また、市町村のウェブサイトにも情報が掲載されていることが多いです。
免除制度の申請方法
免除制度を利用するためには、市町村に申請する必要があります。申請には、所得証明書や戸籍謄本などの書類が必要になることがあります。
申請は、通常、母親が行います。申請を行った後、市町村からの指示に従って手続きを進めていきます。
申請方法と利用条件
母子家庭が国民健康保険料の支援を受けるためには、適切な申請方法を理解し、利用条件を満たすことが必要です。以下に、その詳細を説明します。
申請方法
国民健康保険料の支援を受けるための申請は、居住地の市区町村役場で行います。申請書は役場の窓口で入手できます。申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付した上で、窓口に提出します。
申請書の記入や書類の準備については、役場の担当者に相談することができます。不明な点や困ったことがあれば、遠慮なく質問しましょう。
利用条件
国民健康保険料の支援を受けるための利用条件は、市区町村によって異なることがあります。一般的には、所得が一定の基準以下であること、また、その他の生活状況(例えば、家族構成や住居状況など)が考慮されます。
具体的な利用条件については、各市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせることで確認することができます。また、市区町村のウェブサイトにも情報が掲載されています。
母子家庭の国民健康保険料、計画的に納付しましょう

母子家庭になって収入が減少した時、国民健康保険料の負担は決して小さいものではありません。
しかし、もし滞納状態にあると、受診への心理的な抵抗から治療が手遅れになる可能性もあります。母子家庭でご自身に何かあると生活すべてに影響してきますよね。自分自身や子供の健康維持のためにも、適切に国民健康保険料の負担額を把握し、計画的な納付を心がけましょう。
