母子家庭で安心して生活を続けていくために、購入を考えておいて損がないのがマイホームです。
家を買うための資金は必要となりますが、長く住み続ければ、賃貸の家賃を支払い続けるよりもお得になるケースも少なくないからです。
さらに、いざという時に売却可能な資産を持てる、という安心感も生まれます。
ただ家はとても高い買い物なので、多くは住宅ローンを利用しますよね。それは母子家庭の方でも同じと思います。
でも母子家庭は住宅ローンの審査に通りにくいのでは?と心配する人もいますが、安定した収入を得ている人であれば、ローンを組むことは問題はなく、可能です。
ただし、母子家庭が家を買う際に問題となるのが、母子手当の存在です。
マイホームを変えるほどの収入、余裕があるのだから母子手当は必要ないでしょう、打ち切りです、とならないか、心配ですよね。
そこでここでは、母子家庭で家を買うと母子手当はどうなるのか、続けて支給が受けられるのか、打ち切られてしまうはどんなときなのか、見ていきます。
母子手当で家を買うと母子手当は打ち切りになる?
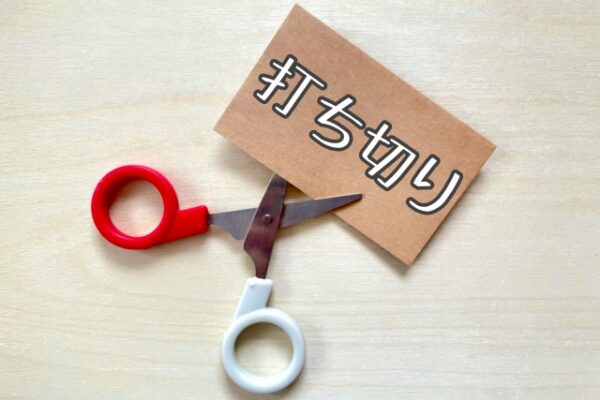
まず、母子手当と言われる児童扶養手当を受け取るためには、所得制限などの条件をクリアする必要があります。
具体的には、同居している扶養状態にある子供が一人の場合、年間の所得が2,680,000円以下に限り、母子手当の支給を受けることができます。(この場合は一部支給。年間の所得が870,000円以下になると全額支給。)
そして同居している扶養家族が増えれば、支給の判断となる所得の金額も多くなります。
普段の収入は母子手当の対象となるものであっても、不動産を取得すると母子手当が打ち切られてしまうのではないかと不安を感じる人は多いものです。
でも大丈夫です。母子家庭の方が家を買うことで母子手当を打ち切られることは基本的にはありません。
購入する家の価格や住宅ローンの金額などに関わらず、仕事によって得ている収入に変化がないのであれば、たとえ家を買ったとしても、そのまま母子手当の支給を受けることができます。
ただし、ここで基本的にはと書いたのは、母子手当を受けるための条件からはずれない限り、という意味です。
では次に、どういう時に家を買うことで母子手当が打ち切られるのか、見ていきます。
母子手当で家を買う、どんな時に母子手当が打ち切りになる?

母子家庭の状態で家を買い、そのまま母親と子供のみでマイホームに住む場合は、継続して母子手当を受け取ることが可能です。
しかし、マイホームに母子以外の人が住む場合は話が変わってきます。
たとえば購入した家に親と一緒に住む場合、世帯収入の計算の仕方が変わってくるので注意が必要です。
というのは、母子手当を受けるために判断される所得は、本人の所得のみではなく、同居する家族の収入も合算して計算されるからです。
家を買う本人の収入は全く変わっていなくても、同居する家族に多額の収入がある場合は、母子手当の所得制限を超えてしまう可能性があります。
所得制限を超えれば、その時点で母子手当の支給は打ち切りとなってしまうため、親との同居を前提に家を買う場合は、世帯所得がどうなるかまで考えておく必要があるのです。
同居する家族の所得についても同じように制限が設けられています。具体的には、同居する子供が一人の場合、同居する家族の所得が2,740,000円以下であれば、母子手当を打ち切られることはありません。
このとき、両親と一緒に住み、両親とも収入がある場合は、両親二人の収入を合わせた所得ではなく、どちらか一方の所得がこの金額を超えなければ母子手当の打ち切りにはならないので、間違えないようにしましょう。
このように、母子家庭の方が収入が多い親と一緒に住む家を購入する場合は、母子手当打ち切りの可能性がありますが、自分と子どもが住む家を購入するだけであれば、母子手当が打ち切りになる心配はありません。
もしあるとすれば、家を購入した後に自分自身の収入が増える場合です。
母子家庭で家を買う、収入が増えると母子手当は打ち切られる?
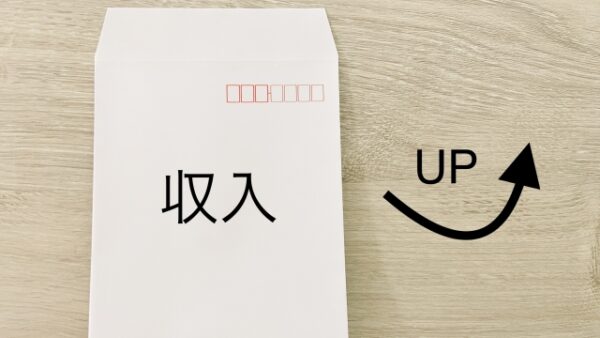
仕事で頑張って収入が増えた、副業をして収入を増やした、少しでも生活を楽にしたいので、収入が増えるのは母子家庭にとってはとても助かりますよね。
でもその一方で、今受けている支援の中には収入を判断基準にしている支援もあり、収入が増えると受けられなくなる支援が出てきます。
難しいのは、所得の金額=数字ですから、支給が受けられる境目ははっきりしています。そのため、この境目を1円でも超えてしまうと、制度上は母子手当を受ける資格がなくなることになります。
こういうのは母子手当に限ったことではありませんが、家のローンという大きな負債を背負っていながら資金的な支援がひとつなくなってしまうわけですから、単に所得が増えればいい、というものではないですよね。
とは言っても、ずっと今の収入のままで生活していくことは難しいでしょう。理想は、支給されている母子手当と同額の収入を仕事で増やすことですが、急には無理な話です。
収入が増えて母子手当がもらえないとなったとき、家計を見直して切り詰めるか、足りない分は親族から一時的に支援してもらうか、パートなど仕事を増やすか、置かれている状況によってできることは変わりますが、こういうことは起こりうることとして、家を買うときに理解しておく必要があります。
また事前にできることとしては、将来的に母子手当が打ち切りになったとしても生活できるような金額の物件にする、住宅ローンの返済額を決める、といったことがあります。新築の物件より中古の物件を選ぶ、といったことです。
母子家庭で家を購入する際の税金控除の利点とその条件

家を購入するという大きな決断をする際、母子家庭の方々には税金控除の利点があります。これは、家を持つことの経済的負担を軽減するための制度で、適用条件を満たすことで利用することができます。
母子家庭が利用できる税金控除の種類とその詳細
母子家庭が利用できる税金控除には、住宅ローン控除や不動産取得税の控除などがあります。これらの控除を活用することで、家を購入する際の負担を大幅に軽減することが可能となります。
ひとり親控除
2020年(令和2年)の税制改正によって新設された所得控除です。所得控除とは、課税対象となる所得金額から一定の金額を差し引くことです。税金は所得金額に基づいて算出されるため、控除できる金額が大きくなると結果として所得税や住民税が軽減されます。
この「ひとり親控除」とは、納税者がひとり親である場合に受けることができる控除です。ひとり親家庭であれば、母子家庭・父子家庭ともに対象になります。また、婚姻歴がなくても対象となります。ただし、合計所得金額が500万円以下でなければ控除を受けられない点に注意しましょう。ひとり親控除の控除額は一律35万円です。
寡婦控除
ひとり親控除のほかにも「寡婦控除」という所得控除制度があり、こちらもひとり親控除同様に所得税および住民税の税制優遇制度となります。寡婦控除の対象要件の1つに女性であることが含まれますが、ひとり親控除と寡婦控除は併用できません。
ひとり親控除の対象となる場合は寡婦控除が適用対象外となるためです。寡婦控除が適用される場合は、控除額は一律27万円となります。
児童扶養手当
国が行っている制度の1つで、母子家庭および父子家庭が支給対象です。母子家庭および父子家庭になった理由は問われません。支給対象者は今年度末(次の3月31日)時点で18歳以下の子どもがいる母子家庭および父子家庭です。支給要件は離婚、親の死亡・行方不明、未婚の母など理由を問わず、支給額は子どもの人数や年齢、所得により異なります。
また、児童扶養手当は所得による制限がありますが、所得が一定額以下の場合には全額が支給されます。この手当は、子どもを養育するための費用を補助するためのもので、家を購入する際の費用を補助するものではありませんが、生活全般の支援として利用することができます。
これらの税金控除や手当を活用することで、母子家庭でも家を購入する際の負担を軽減することが可能です。しかし、それぞれの制度には詳細な要件があり、適用されるかどうかは個々の状況によります。具体的な手続きや適用条件については、最寄りの市役所や区役所、税務署に問い合わせてみてください。
母子家庭が家を購入する際の住宅ローンの審査について

家を購入するためには、多くの場合、住宅ローンを利用します。しかし、住宅ローンの審査は厳しく、母子家庭の方々が審査を通過するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
住宅ローンの審査基準と母子家庭が審査を通過するためのポイント
住宅ローンの審査では、収入や勤続年数、借入金額などが考慮されます。母子家庭の方々が審査を通過するためには、これらの要素をしっかりと準備しておくことが重要となります。
審査のポイントは大きく分けて3つあります。
収入
金融機関は、借り手の収入を確認します。これは、借り手がローンを返済できる能力があるかを判断するためです。母子家庭の場合、収入源は主に仕事の収入と母子手当になります。これらの収入が安定している必要があります。
信用情報
金融機関は、借り手の信用情報をチェックします。これには、過去の借入れ履歴や遅延返済の有無などが含まれます。信用情報が良好であることが、審査を通過するための重要なポイントです。
借入れ金額と物件価格のバランス
金融機関は、借入れ金額と物件価格のバランスを見ます。物件価格に対して借入れ金額が適切であることが重視されます。
母子家庭が住宅ローンの審査を通過するためには、これらのポイントを意識することが重要です。また、金融機関によっては、母子家庭向けの特別な制度を設けている場合もあります。具体的な審査基準や制度については、各金融機関に直接問い合わせてみてください。
母子家庭が家を購入する際の住宅ローンの利用方法とそのメリット

住宅ローンは、家を購入するための重要な資金調達手段です。しかし、その利用方法やメリットは十分に理解しておく必要があります。母子家庭の方々が住宅ローンを上手に利用するためには、その特性や利用方法を知ることが大切です。
住宅ローンの利用方法とそのメリット
住宅ローンの利用方法は、大きく分けて2つあります。一つ目は、金融機関から直接借り入れる方法です。この方法のメリットは、審査が比較的早く借入額の自由度が高いという点です。しかし、金利は高いというデメリットがあります。
二つ目は、公的な住宅金融支援機関を利用する方法です。この方法のメリットは、金利が低めに設定されているという点です。しかし、審査に時間がかかることや、借入額に制限があるというデメリットがあります。
どちらの方法を選ぶかは、個々の経済状況やニーズによります。しかし、どちらの方法を選んでも、住宅ローンの最大のメリットは、大きな資金を一度に用意することなく、自分の家を手に入れることができるという点です。
また住宅ローンの利息は所得控除の対象となるため、税金の節約にも繋がります。さらに自分の家を持つことで、賃貸物件に比べて住環境の自由度が高まり、生活の安定感も増します。
ただし、住宅ローンを利用する際には、返済計画をしっかりと立てることが重要です。毎月の返済額は、収入や生活費など、自身の経済状況に合わせて設定する必要があります。また、金利の動向や自身の生活状況の変化など、将来的なリスクも考慮に入れておくことが求められます。
住宅ローンを上手に利用することで、母子家庭でも安心して自分の家を持つことが可能です。しかし、そのためには、住宅ローンの利用方法やメリット、そしてリスクをしっかりと理解し、自身の経済状況に合った計画を立てることが大切です。それにより、母子家庭でも安定した生活を送ることができるでしょう。
母子家庭で家を買う、母子手当がなくなっても資産が残ります

マイホームがあれば、安心して子供と住むことができます。また賃貸では、部屋の大きさや数、模様替えやリフォームなど、色々と制約がありますが、自分の家なら何をしても自由ですよね。子供も、自分の家ならのびのび暮らすことができるでしょう。
そして家は、生活を楽にしてくれる可能性があるだけでなく、将来的に子どもに残してあげることができる資産にもなります。
家を買うことを迷っているのであれば、母子家庭だからと諦めず、前向きに検討してみることをおすすめします。
